【ドクターインタビュー】
病診連携で診るDME治療
~専門医と一般眼科医で支える抗VEGF薬治療
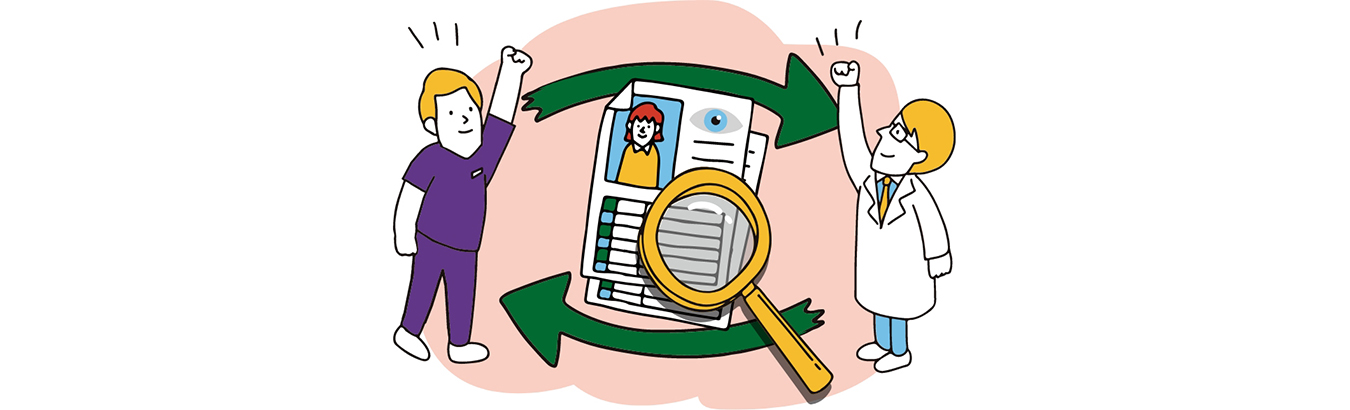
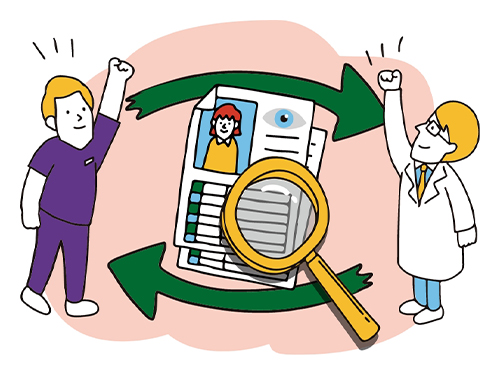
一般眼科医からの専門医への患者紹介
紹介患者さんは全て受け入れ、治療法は一から説明しています
埼玉医科大学病院眼科(当科)では、基準を設定せず、軽症例を含め一般眼科から紹介される全てのDME患者さんを受け入れています。DMEの場合、加齢黄斑変性(AMD)と比べ既治療例の紹介が多いという印象があります。DMEはAMDよりも疾患概念としての歴史が長く、診断基準や複数の治療法が確立されているため、一般眼科医でも診断しやすく治療を試みやすいという面があり、こうした違いが生じていると推測しています。最も多い紹介理由は治療の効果が得られないというもので、中でも抗VEGF薬は高価なため、開業医では1回目の投与で効果が得られなければ2回目の投与を勧めづらいようで、その時点で紹介される患者さんが少なくありません。
軽症の場合は「状態が悪いから専門医に紹介されるのか」と不安になる患者さんもいますので、専門施設での治療によって症状を安定させるといった説明をしてもらうといいと思います。特に、治療途中での紹介は、治療法の説明が不十分だと患者さんが不信感を持ちかねないので、コンセンサスを得ることはとても重要です。私は治療を始める際には、“治療を整える、仕切り直す”という心構えで一から治療法を説明します。患者さんに正しい知識を伝えることで、紹介元や近隣医への引き継ぎ後も治療が継続できるように配慮しています。
紹介前における抗VEGF薬の投与間隔は治療の検討において重要な判断材料になります
既治療の患者さんを紹介する際には、抗VEGF薬治療を含めて、それまでの治療内容と治療前後の画像所見を提供してください。また、もし効果がないと判断した場合は、その根拠があると治療方針を決める上で大きな手掛かりになります。抗VEGF薬治療に関しては、投与回数、投与日、投与間隔を共有してほしいです。とりわけ投与間隔の変化は、効果の程度や病状の変化に加え、他の糖尿病合併症との関連を推測するのに重要な材料になります。
DMEでは徐々に視力が低下する傾向があるため、初期段階では治療を開始すべきかどうかの判断が難しいことがあります。そうしたグレーゾーンについての判断をするのが専門医の仕事だと思いますので、もし判断に迷い未治療で経過観察としている場合は、早めに専門医に紹介してください。
一般眼科医に引き継ぐ重要性
病診連携は専門医・一般眼科医・患者全てにメリットがあります
視力の改善や維持の達成、浮腫の退縮など症状が安定すれば、基本的に紹介元の施設に治療を引き継ぎます。手術と異なり、抗VEGF薬治療は一生を通じて必要となるため、通院のしやすさや待ち時間の短縮、治療アドヒアランスの向上、増悪の早期発見といった点を考慮すると、近医で継続することが望ましいです。大学病院などの専門外来で1日に診療できる患者数には限りがあり、担当医の負担軽減という面からも、症状が安定した患者さんの治療を一般眼科医に引き継ぐことは専門医にとってもメリットがあります。
専門医での治療により症状が改善した患者さんが戻ってくることで、一般眼科医は有効な治療についての情報が得られるだけでなく、紹介者として患者さんからの信頼も高まります。また経営の観点からも、再診患者が増えることはメリットになると思います。
さらに、専門医で実施済みの治療を継続する形であれば、自施設で新規に導入するよりも実施のハードルは低くなります。病診連携により専門医のサポートを受けられる環境が整ったことで、自施設で抗VEGF薬治療が実施できるようになったというケースもあります。中でもブロルシズマブは眼内炎症(IOI)の発現リスクがあるという理由から1)、一般眼科医は使用を敬遠する傾向がありますが、専門医での治療を引き継ぐ形であれば、使用できるようなることが少なくありません。病診連携によって近医でブロルシズマブを導入できれば、治療の選択肢が広がり患者さんのメリットになります。加えて、DMEは改善した後も維持管理のため定期的な通院が必須となることから、近医での継続治療は患者さんの通院負担の軽減にもつながります。
連携体制の構築におけるポイント
薬剤の使い方を見極め、治療プロトコルを公開しています
当科では、ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)、企業主催の講演会、地域勉強会などで病診連携に関する情報を発信しています。地域の医師会を通じて情報を得ている開業医も多いようです。
新規薬剤を普及させる上では、大学病院などの中核施設がある程度のリスクを背負い、安全な使い方を見極める役割を担うべきだと考えます。そのため当科では、重症度にかかわらず全ての紹介患者を受け入れ、治療実績を積み重ねることに注力しています。集積した治療実績を基に、地域の開業医やクリニックで行える治療プロトコルを作成し、連携施設との勉強会などで公開しています(図)。
紹介元に患者さんを引き継ぐときには、推奨治療や治療プロトコルを提供しますが、医師ごとにやり方やポリシーがあると思いますので提案にとどめています。一方、プロトコルに則した治療が無効なケースでは、専門外来での治療内容と結果を詳細に伝え、現在の症状や治療の効果を認識してもらいます。こうしたやり取りが医師間での良好な関係を築くものと考えています。
(吉川祐司先生提供)
“最も効果を得られたとき”の画像との比較がIOIの早期発見につながります
病状の改善が得られると、医師は治療に対する熱量が下がって、軽微な再発を見逃しやすくなります。特にDMEでは徐々に症状が悪化するため、直前の画像所見と比べても変化に気付かないことがあります。常に“最も治療効果が得られたとき”の画像所見と比較することが極めて重要になります。
ブロルシズマブを使用する施設には、IOIを早期に発見する体制の整備が求められ、早期発見には光干渉断層計(OCT)を用いることが有用です2)。また、患者教育だけでなく、受付や看護師などのスタッフ教育が欠かせません。医師の診察よりも、電話や受付での応対が早期発見の入り口になります。電話をする時点で患者さんは不安を感じているので、直ちに受診を勧めるべきです。
病診連携における抗VEGF薬治療の進め方
未治療例では導入期の3回投与を徹底します
抗VEGF薬治療は、DME治療における第一選択の位置付けになると考えています。ただし、抗VEGF薬は硝子体牽引や硝子体出血など明らかに手術の適応がある場合は除外し、心筋梗塞・脳梗塞急性期後6カ月以内の場合にも使用は避けます。さらに、ブロルシズマブではIOIの発現リスクに鑑み、これらに加えて単眼患者、炎症既往や血管閉塞既往のある患者への使用も控えます。
未治療例に対する抗VEGF薬治療では、導入期の3回投与を徹底します。そうすることで、維持期にpro re nata(PRN、症状の悪化時に随時投与)法による投与が可能になります。また、当科では、切り替え例においては1+PRN法を基本としていますが、初回投与時の効果や切り替え前の状況によっては再導入期を設けたり、treat and extend(TAE、症状の改善に合わせて投与間隔を延長)法で投与することもあります。導入期に効果が見られない場合は、複数の抗VEGF薬を試すのではなく、光凝固術や硝子体手術を適用すべきだと考えます。ただし、ブロルシズマブ未使用の場合には、手術適応と判断する前に一度はブロルシズマブを投与しています。
*日本において承認されたDMEに対するブロルシズマブの用法および用量(抜粋):
ブロルシズマブ(遺伝子組換え)として6mg(0.05mL)を6週ごとに1回、通常、連続5回(導入期)硝子体内投与するが、症状により投与回数を適宜減じる。その後の維持期においては、通常、12週ごとに1回、硝子体内投与する。なお、症状により投与間隔を適宜調節するが、8週以上あけること。
導入期の3回投与後を目安に治療を引き継いでいます
導入期の3回投与後に中心窩網膜厚(CFT)が320~350μmに退縮すれば、そのタイミングで紹介元に治療を引き継いでいます。専門医での治療継続を希望する患者さんもいますが、長期にわたり向き合う必要がある治療なので、「私たちのような勤務医は異動や退職があるので、長く診てくれる近隣の先生と信頼関係を築いてください」と伝えています。逆に、仕事を持つ患者さんでは、夕方や夜、土曜に受診できる近医に早く戻りたいと希望される場合があります。
病診連携によるサポートがもたらす安心感
視力が良好でも、網膜構造の崩壊は進んでいることがあります
「DMEだけど、視力が良好だからOCT検査や治療はしない」という声を少なからず聞きます。しかし、自覚検査に基づく視力と形態学的な構造の変化は、必ずしも同時に起きません。通常は網膜構造の崩壊が先行して生じ、時間差で視機能の低下が起こるので、浮腫や異常な形態が見られたら直ちに専門医に紹介してください。こうした時間差が存在するゆえ、治療の要否判断が難しいケースや視力が良好な患者さんを説得できないことがあると思いますので、そのようなときには専門医を頼ってほしいです。
抗VEGF薬治療の効果を得るには早期の治療開始が肝要です。有効な薬剤であっても、不可逆的な障害を来した後では治療は難渋します。この意味において、治療は視力低下が起きる前、浮腫を確認した時点で開始するのが望ましいです。また、もし視力低下が起きていても、早期であれば患者さんは視力の改善を実感しやすいことから、治療継続のモチベーションが向上します。
IOIへの対応やリスク期間は専門医に任せ、安心して治療を引き継いでください
現在日本では、バイオシミラーを含め4種類5製剤の抗VEGF薬が使用できます。それぞれ特徴に合わせて使用されていますが、ブロルシズマブは浮腫軽減の効果があり、投与間隔を延ばせる可能性があるものの1)、IOI発現に対する懸念のため、引き継ぎ後に継続が難しい場合があります。しかし、IOIは早期に発見できればステロイドの点眼やトリアムシノロンのテノン囊下注射(STTA)などによる対応法があります。そのため、クリニックなどでは常にIOIの早期発見を念頭に置き、もしIOIの症状が見られたらOCTなどの検査結果を記録した上で、対応自体は専門医に依頼するという選択肢があります。
私は、一般眼科医が“困ったケースには紹介という手段がある”という安心感を持てるように、大学病院をはじめとする専門外来があると考えています。患者管理が難しい初回投与後の半年~1年の期間は専門医での治療とし、症状の改善や維持が得られた時点で一般眼科医が引き継ぐというのも1つの方法でしょう。
患者さんにとっては身近な開業医やクリニックが治療への入り口になりますので、病診連携による患者紹介はとても重要です。DMEでは、ある日突然、患者さんが視力低下を訴えるケースが少なくないため、発見した際は積極的に治療することを推奨します。ただ、一般眼科医は治療に躊躇、難渋したり、患者さんが治療に対し抵抗感を示すというような悩ましい場面があると思います。病診連携を活用することで治療のハードルはぐっと下がりますので、悩んだときには専門医に紹介状を書いていただきたいです。また、知識の共有や治療水準向上のため、地域における病診連携の勉強会などには積極的に参加してほしいです。専門医と一般眼科医が良好な関係を築くことで、抗VEGF薬治療を支えていくのが望ましいと思います。
文献
1)Wykoff CC, et al. Am J ophthalmol 2024; 260: 70-83.
2)Yoshikawa Y, et al. Case Rep Ophthalmol 2021; 12: 797-803.
*文献1は、ノバルティスの資金により行われた。本論文の著者のうち4名はノバルティスの社員、7名はノバルティスの顧問、1名はノバルティスのアドバイザーである。著者にはノバルティスより講演料/研究費/助成金を受領している者、ノバルティスの資金により行われた他の試験にも参加した医師が含まれる。100週時のデータは承認審査過程において当局に提出しており、社内では評価されたものと見なしている。


